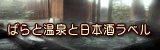| 冬住みの里資料館 |
|
 |
湯の平温泉入口から国道292号(旧道)を長
野原方面へ進むと、ほどなく右手に冬住みの
里資料館が見えてくる。
ここは六合村小雨地区。村役場や郵便局が
ある、村の中心である。ここを通る暮坂道は
戦国時代、信州上田と上州沼田に城を持つ
真田氏の軍用道だった。さらに江戸時代にな
ると、草津、沢渡、四万、伊香保と温泉街道
として多く利用された。若山牧水の『みなかみ
紀行』の舞台としても有名である。 |
草津温泉の標高は1200m、ここ小雨地区は
700m。標高差は500mで、湯治客で賑やか
な草津も冬が来ると客足も途絶えて雪の中。
そこで旧暦の9月末、今の11月8日に草津
温泉の人々は一斉に東向きの谷あいのこの
地へと移り住み、湯治客の生活用品の仕度
や土産物作りをした。そして5月8日になると
草津へと戻っていく。そのためここは別名、
冬住み村と呼ばれた。村人は小雨、草津の
両方に家を持っていたのだ。 |
 |
明治21年4月、市町村制の発布により、小雨、草津、前口、太子、日影、生須、赤岩、入山
の8つの集落が合併して草津村となったが、明治33年7月1日に分村した。草津温泉が世
界的に有名になり、冬でも住める環境が整ったためである。草津、前口は草津町となり、他
の6集落は合わせて「六合」、古事記の中の「天地四方(六)をもって国となす」から「くに」と
読ませる六合村(くにむら)となった。 |
 |
武田家の家臣を祖先に持つここ市川家には、
戦国時代から昭和に至る数々の文化財が残
されている。草津の温泉街は幾たびか火災
に遭ったが、冬住みの里には草津を訪れた
人々が持ち込んだ貴重な品々が残ったのだ
という。
以前は「大黒屋」の屋号で民宿を営んでいた
が、ご主人の定年退職を機に夫婦で2ヶ月半
かけて土蔵の中を整理し、平成7年に資料館
として公開した。 |
古伊万里の大どんぶりや皿、武田菱の入った矢筒、小林一茶の短冊、佐久間象山や円山応
挙、西郷隆盛、横山大観らの書画、輪島塗の大名膳、水戸黄門の家臣が書いた草津温泉賛
美の漢文、日露戦争の祝杯、温泉を引く木管を作るための巨大な手動ドリル、明治時代の草
津の様子を描いた絵図・・・数え切れない品々が所狭しと展示してある。母屋の直径62cmの
大黒柱も見ごたえがある。
3つの蔵をご主人自ら丁寧に解説しながら案内してくれ、見学した後は母屋の茶の間で奥さん
がお茶や自家製の漬物をご馳走してくださり、世間話に花が咲く。田舎の親戚を訪れれたよう
な温かい時を過ごせる場所です。 |
【所在地】群馬県吾妻郡六合村大字小雨540 電話 0279(95)3563
【入館時間】午前9時〜午後4時
【入館料金】大人500円・小中学生200円
【休館日】不 定 |