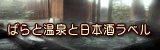| ����h�@�`�Q�n���a��s�`�@�i2007�N�P���W���j |
|
 |
���Â���̋A�蓹�A����17�����i���o�C
�p�X�j�����̓��̉w�u�������v�ɗ������܂�
���B�x�����H���Ƃ邽�߂ɓ������H���̑�
���猩�����u����h�v�̊Ŕ��C�ɂȂ�A�H
��ɂԂ��Ƃ��Ă݂܂����B
���̎ʐ^�͔���h�̖k�̓����B��ʂ̌���
���V17�������瓹����{�������Ƃ���ɁA
����ȏ����������Ƃ́E�E�E�B |
|
�ǂ��܂ő����Ă���̂ł��傤�B���̐^�𗬂�鐅�H�ɓ������悤�ɕ����Ă���ƁA
�₪�Ď艟���Ԃ������ɂ������ƕ����Ă��邨�N����ǂ������܂����B |
�@�E�E�����B
�u�����v�Ɛ���������ꂽ�̂͏��߂āB�v�킸
�u���ꂪ���ł�����܂��邩�v�Ɖ��������ɂȂ�
�܂����B
�@�E�E�����Ԃ�������Ȃ炱�̒n�̐��������܂����B
�@�@���}���ł����H
�X�L�[�A��̎Ԃō��ޑO�Ɋ։z������
�������̂ł����A���j�A���ɋ��X����h��
�ɋ���������̂ŁA���ꂩ���t�ɋA��Ȃ�
��Ȃ�Ȃ����Ƃ����f�肵�������ŏ�������
���肢���邱�Ƃɂ��܂����B�艟���Ԃ̒��ɂ�
���q��������ψ��������p���t���b�g��
������������Ă��āA�ǂ����{�����e�B�A�Œ�
�̈ē����Ȃ����Ă�����̂悤�ł��B���Ƃł�
�N�����̂ł���87�������ł��B |
 |
| �ȉ��͂��̐����ƃp���t���b�g�����Ƀ��|�[�g���܂��B |
|
|
�u����h�v�Ƃ����ď̂����A�����ȈӖ��ł�
�h�꒬�ł͂Ȃ��B
�Õ����ɂ́u���߁v�̋L�q�������邪�i����
�n�̗̎�̉����������߂��܂Ƃ��Ă�������
�ɗR������Ƃ��j�A��˂ւ̑A�]����u��v��
���Ă�悤�ɂȂ����Ƃ����B
15���I�����A������ƌ�Ȑ�̍����n�_��
���o���͊ݒi�u��ɔ���邪�\�z���ꂽ�B
������30m�قǂ̒f�R�ɂȂ��Ă���A�n�`��
���p�����V�R�̗v�ǂł������B ���͊֓�
�Ǘ̏㐙���̔z���ł��锒�䒷�����B�z��
�̖��l�ł��鑾�c�����̓��������A ����
�l�ĂƓ`���W�������c��B
��̓����̋u�ˉ��ɂ͒�����ړI�Ƃ��Ē�
�l�E�_�����W�߂��A�鉺���Ƃ��Ĕ��W�B��
���̒��̌��`�ƂȂ����B |
 |
|
|
�����ɂ��u�h�꒬�v�炵���i�ς�����Ă���̂�����
���䉁�B�̂��ɒ��̐����p���H�ƂȂ������̂́A��
���̖��ō��ꂽ�����͉J���̔r���a�ŁA������
�ג��������݂𗘗p���Ĕn��ɂ���Ă��܂����B��
�̒[����[�܂ł͖�P�����B�����ƂQ��肷��Ƃ���
���ꗢ�ƂȂ邽�ߔn��ɂ͂����Ă��Ƃ����킯�B��
�s�l�͔n�������Ă���Ɣ��Α��̓��Ɉړ����A�Z��
�͓��Ȃ炵�ɒǂ��鎞�����������Ƃ����B
���a22�N�ɔ_�Ɨp���H�ƂȂ�A���݂͌Q�n�p����
�������B |
|
 |
|
|
��P�q�̊ԂɂW�̈�˂�����B�鉺������ɂ͏Z��
�̈�ˌ@�肪�ւ����A���S���[�g�������𗬂�闘
����܂Ő������݂ɍs���Ȃ���Ȃ炸�A��˂�����
���Ƃ͏Z���̔ߊ肾�����B�㊯�����ƂȂ��ˌ@�肪
�����ꂽ���̂́A�@��ƃK�X���o�A�����܂ł͂R�`
�S��i11�`15m�j�̐[���܂Ō@��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B |
�Â��͍]�ˏ���(1624)�Ɍ@��ꂽ�u��t�̈�ˁv����
���a�S�N(1929)�Ɍ@��ꂽ�u�{�{���̈�ˁv�܂ŁA�W��
�̈�˂͌͂�邱�ƂȂ������ŗ��p����Ă���B |
 |
|
�����̓^���N�ɂȂ��Ă��ă|���v
�A�b�v���ꂽ��ː��������̊e
�˂ɋ�������Ă���B
|
|
|
 |
�퍑������o�Ď��X�Ə�傪�ς������A
�]�ˎ��㏉���ɔ����͔p��ƂȂ�A����
�i�����̂ڂ�j�㊯�̎��߂�Ƃ���ƂȂ����B��
���͓�k�ɍג������̌`�𗘗p���A�Z���`
�̒�����������B���̖k�[�ɖ،˂�݂���
�����J�����c���ʂƘA������ƁA�O���X���A
���ÊX���ɂ��ڑ������ʂ̗v�ՂƂȂ�A
�Z�Ďs���J�����s�꒬�Ƃ��ē�������B
�����̗��l���������A�����݂���u�h�v�Ƃ���
��A���ꂪ�{�w�E�l�n�p���Ƃ������h��@
�\�������Ȃ����̒����u����h�v�Ƃ�����
���Ȃł���B
|
��������ɂȂ��ĂP�q�قǏ㗬�Ɍ�ȋ���
�����萴���z�����i���݂�������������E���݂̍�
��17�����j�̃��[�g����O���ƁA�s�꒬�͋}
���ɐ��ނ��A�_�Ƃ���̂Ƃ����W���ɕϗe��
�]�V�Ȃ����ꂽ�B
����32�N�̑�ɂ��Â��Ɖ��͏��Ȃ���
�̂́A�������ĕ���̂��铹�͎c���ꂽ�B��
�O�͉������E�ɂ��ė��������̉Ƃ�������
��̂悤�ɗ��p���A�~�̖�A���Ă�������
�����A���ς��l����20�N�قǑO�ɔ��d����
���S�Ƃ�����̖ɐA���ւ����Ƃ����B���N
�S���̍ŏI���j���ɂ͐���ɍՂ肪�s���A
���ҍs��������B |
 |
|
|
�����͍]�˒���(1746)�B���̖،˂��k�ɂ��邽��
�k���Ɉ��u����Ă���B��O�ɂ������i���j��
���āi�E�j�͒j�_�E���_�̑o�ɂȂ��Ă���B |
|
 |
|
 |
�u�n�_�i������j�v�Ə�����Ă���B
������1828�N�B�ˑq���i�����S
�Еi���j�o�g�̏��ƁE�����a�i��
������ȁj�̏��B���̗t�𑩂˂�
������M�ŏ�����A�u���a�̍�
���v�Ƃ����Ă���B |
|
|
���̑��ɂ���˂��@������Ԋ^���o�Ă����ȂNj����[���b����������f���܂����B�鉺�������
�����݂ŋ�J�������Ƃ⒬���n��ɂ���Ă��܂����Ȃ炵�ŖZ�����������ƁA����ɂ͗��̏��Ƃ�
���̕M�Łu�n�_�v�Ə����Ă���������ƂȂǂ��A�������������g�����̏�ɋ����킹�����̂悤��
�����̂Ŏv�킸���������Ă��܂��܂����B�����قŃ{�����e�B�A�ŏ����������Ă�����Ƃ�
���ƂŁA�u�����v����b�͏��̍u�߁A�����̐��藧���ɂ܂Ŋg�債�A�u�������͂��낻��E�E�E�v�Ƃ���
�Ƃ܂������͂P���Ԕ����o�߁B�z�����Ȃ�X���Ă��܂����B�M������Ă����������̂ł����A���
�芦���B�k���͔����h���A�Ȃɂ������Ă����̃x���`�̗₽�����ƁB��������������������̂�
�₦�����Ƃł��傤�B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�Ⓚ�}�O����ԂɂȂ�����X�́A�����a�͊o�債�A�\��ɂ͂Ȃ������u���䉷�����̓��v��
�̂����߂ɍs���܂����B |
|
 |
�y�NjL�z 2008�N�S��26���̗[��ꎞ�A��������Ă݂���
���d�������J�ł����B |
 |