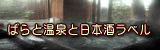| 西山荘(せいざんそう) (2003年9月6日) |
大子温泉へ向かう途中、常陸太田(ひたちおおた)の西山荘に立ち寄りました。
|
 |
黄門様ファンとしては是非おさえておきたいス
ポット。今回は久しぶりの訪問となりました。 |
| 入口付近には杉の巨木がうっそうと |
|
 |
元禄3年(1690年)10月、水戸藩第二代藩主
徳川光圀公は、63才で家督を兄の子綱條(つ
なえだ)に譲り、翌元禄4年5月に完成間もな
い西山荘に移り住み、元禄13年(1700年)に
73才で亡くなるまでの10年間をここで過ごしま
した。 |
光圀公が紀州から取り寄せた熊野杉
樹齢は約320年、樹高約50メートル |
 |
 |
家督を譲った後、権中納言に任ぜられました
が、この官位の唐名が「黄門」(都の黄色い門
を出入りできる高位から)だったので「水戸の
黄門様」として人々から尊敬され、また慕われ
ました。 |
| 光圀公が考案した跳ね上げ式の門(写真左手) |
|
 |
テレビの「水戸黄門」では各部の第一回目は
いつもこの西山荘から始まり、家老山野辺兵
庫を煙に巻き、助さん・格さんを従えて旅立つ
のですが、黄門様の諸国漫遊は江戸後期以
降の作り話で、実際にはここで穏やかな隠居
生活を送ったわけです。 |
| 素朴で穏やかな佇まい |
|
 |
ところで、日本で初めてラーメンを食べた人、
初めて牛乳を飲んだ人は誰だかご存知でしょ
うか。そう、黄門様なのです。そうした好奇心
旺盛なところと、身分の別なく多くの領民を西
山荘に招いて親交を重ねたという人柄から、
諸国漫遊というフィクションが生まれたのでし
ょう。 |
先の副将軍の住居ながら
威圧感を全く感じさせない玄関 |
 |
 |
光圀公はただ楽隠居していたわけではありま
せん。日本の歴史をまとめるという『大日本史』
編纂事業をこの西山荘で行いました。
助さんのモデル・佐々介三郎は全国を巡って史
料収集を、格さんのモデル・安積覚兵衛は光圀
公の下で編纂に当たったそうです。
『大日本史』編纂事業は光圀公の死後も続けら
れ、完成したのはなんと明治39年(1906年)の
ことでした。 |
| 二畳半の質素な書斎 |
 |
 |
テレビの黄門様は、東野英治郎、西村晃、佐野
浅夫、石坂浩二、里見浩太朗とリレーし、風車の
弥七もうっかり八兵衛も柘植の飛猿も過去のキ
ャラクターとなってしまいました。
本物の光圀公も、遠い昔の日本も、テレビの歴
代黄門様も架空のキャラクターも何もかもすべて
ひっくるめて懐かしくなる・・・西山荘は訪れると
そんな気持ちになる場所でした。 |
| 西山荘に佇むお銀? |
|
|
|
【所在地】茨城県常陸太田市新宿町590 電話 0294(72)1583
【入館時間】午前9時〜午後4時30分
【入館料金】大人500円・小学生250円
【アクセス】常磐道日立南太田ICから国道293号経由約25km /
JR水郡線常陸太田駅よりタクシーで10分 |
|