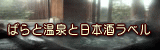「立ち寄りスポット」で紹介しますが、東山魁夷画伯も何度かここに滞在されたそうです。あの唐招提寺障壁画の作成中も骨休めに訪れたとのこと。
宿から5分ほどのところには画伯の絵『緑響く』のモチーフとなった御射鹿池があります。 |
 |
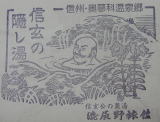 |
戦国時代の武将・武田信玄が、上杉謙信との戦いのために八ヶ岳山麓に「信玄の棒道」(甲斐から善光寺平にいち早く出るための軍用道路)を建設。この湯の薬効に注目し、傷兵を湯治させたといいます。 |
|
| 以来「信玄の薬湯」と呼ばれ、江戸時代中期から昭和初期までは湯を樽に詰めて薬として販売していたそうです。 |
 |
 |
 |
| 脱衣所には「薬湯の湯壷は約三尺(90cm)の深さがございます。御入浴の祭は御注意ください」という貼り紙と深さを示す板があります。 |
湯舟は3つあり、真ん中は
打たせ湯になっています。 |
 |
| ここの湯は冷たい硫黄泉。浴室は硫黄香が立ち込めています。 |
では、さっそく・・・と足を入れたら・・う〜、冷たい!
これは源泉そのままの冷泉の湯舟。源泉温度は26.4度だそうですが、湯舟まで引いてくるまでにさらに温度が下がっているようです。 |
 |
 |
入れかけた足を引っ込めて、先ずは加熱した湯舟の方から入るとします(軟弱者です)。
脱衣所の注意書きのとおり浴槽はかなり深く、中腰で入る感じになります。無加熱の方も同じ深さですが、白濁していて底が見えないので注意が必要です。 |
| 加熱槽と無過熱槽とはわずかながら木管でつながっており、両方の湯舟を微妙に温度調節しています。 |
 |
 |
入口に一番近い湯舟も無加熱の冷泉。
加熱槽とつながっていない分、真ん中の湯舟よりさらに冷たい感じです。
温かい湯と冷泉と交互に入るうちに体はぽっかぽか。時たまほろずっぱい硫黄泉を口にして・・・外から内から癒されます。 |
|
| 内湯を満喫したあとは露天風呂へ |
 |
 |
| 「森の温泉」と名付けられた露天風呂の浴槽は2つ。 |
 |
 |
加熱してありますが、露天のため
かなり温めのお湯です。 |
あたりは一面の白樺林 |
温泉浴と森林浴を同時に楽しめて・・・
あ〜〜・・
言葉が見つかりません。 |
 |
 |
もうひとつの湯舟は屋根がある分
もう少し温かめのお湯です。 |
| ケロリン桶に出会えたのもうれしい |
 |
|
 |
ひと風呂浴びたあとは森林浴 |
 |
 |
渋・辰野館の周囲は
ハイキングコースになっています。 |
さわやかな渓流 |
 |
 |
| 深い原生林 |
美味しいかな? |
 |
 |
| 約8万本の白樺林 |
ヒカリゴケ |
 |
 |
| 8月下旬、もみじが色づき始め・・ |
風は秋色です |
蓼科山(標高2530m)も間近。
昔、あの山頂に立ったこともあったっけ・・ |
 |
|
 |
散歩の後はまたひと風呂。
湯温が下がらないように、誰も入っていないときは蓋をします。
一泊二食で16000円。食事は食堂でいただく山の宿では普通の内容ですが、とにかくお湯が素晴らしい。チェックインからチェックアウトまでに内湯「信玄の薬湯」と露天風呂「森の温泉」のセットを6回楽しみました。 |
| 【また行ってみたい度】 →こちらをお読みください |
| やなぎ夫: |
★★★★☆ |
やなぎ妻: |
★★★★☆ |
|
2003年8月23日 |
|