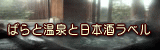| 奈良井宿 〜長野県塩尻市奈良井〜 (2010年8月18日) |
|
| 奈良井宿は中山道六十七宿のひとつ。江戸側から数えても京都側から数えても34番目、中山道の真ん中の宿場町で、難所の鳥居峠を控え、峠越えに備えて宿をとる旅人が多く、「奈良井千軒」と謳われるほどの賑わいをみせました。 |
 |
| 奈良井は、戦国時代に武田氏の定めた宿駅となっており、集落の成立はさらに古いと考えられています。慶長7年(1602)江戸幕府によって伝馬制度が設けられて中山道六十七宿が定められ、奈良井宿もそのひとつとなりました。 |
|
奈良井川に沿って約1kmにわたって町並みが続いています。旅籠の軒灯、千本格子など往時の面影を色濃く残しています。
奈良井宿は街道に沿って南側から上町、中町、下町の三町に分かれ中町に本陣、脇本陣、問屋などが置かれていました。 |
 |
 |
昭和53年に国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け、また平成元年には建設大臣の「手づくり町並賞」を受賞。平成19年には「美しい歴史風土100選」に選定されるなど、美しい町並みとそれを保存している住民の皆さんの努力が評価されています。 |
 |
 |
| 理容店も自動販売機も町の美観を損なわないように配慮されています。 |
|
|
 |
街道沿いに6箇所の水場があり、住民の生活用水として今も現役で使用されています。 |
 |
 |
| この夏は木曽路も大変な猛暑でしたが、水場の清水は氷を入れたように冷たくて気持ちいい。 |
|
|
|
|
 |
| 奈良井宿には背後の山裾に5つの寺院が配されています。大宝寺はそのひとつで、創建は天正10年(1582)。境内にはマリア地蔵尊が祀られており、案内板によると「この石像は、昭和7年(1932)の夏に、地元の人が藪のなかになかば埋もれているところを掘り出したと伝える。抱かれる嬰児が手にもつ蓮華の先が十字状になっているところから、隠れキリシタンが観音像をよそおってひそかにまつったものではないかと言われている」とあります。 |
|
|
|
 |
道の駅「奈良井 木曽の大橋」
JR中央本線を挟んで町並みの東側にある商業施設がない珍しい道の駅。木曽の大橋は総桧造りの太鼓橋で、橋脚を持たない橋としては日本有数の大きさです。 |
|
| 「山なか」の手打ち蕎麦、美味でした。宿場の南端近くにあります。 |
 |
 |
|
 |
日野百草本舗で百草丸を買いました。百草丸は江戸時代から伝わる「百草」のキハダの内皮を煎じたオウバクエキスに、5種類の生薬を配合した胃腸薬。 |
寛政5年(1793)創業の造り酒屋、杉の森酒造。
もちろん買ってきました。すっきりした味わいの美味しい酒です。 |
 |
 |
|
奈良井宿でぜひ紹介したいのが藤屋土産物店。土人形、土鈴、木製カラクリ玩具、民宿ミニチュア、版画などのオリジナル商品が並んでいます。
残念ながら今回訪れた時は休業日でしたが、十数年前に訪れた折に求めたものをご紹介します。 |
 |
 |
| そば食い猿 |
|
 |
 |
| こちらは奈良井宿に実際に存在する民宿「しまや」のミニチュア。千本格子、二階の軒に張り出した縁側、石置き屋根から内部の襖絵に至るまで、細かい作業が光ります。暖簾には我が家の家紋も入れてくれました。すべて手作りで、注文順に作成するため、届くまでに10ヶ月ほどかかりました。 |
| 一階は飲めや歌えのドンチャン騒ぎ、一方二階では江戸から駆け落ちしてきた二人が・・・ |
 |
 |
| 芸が細かい。 |
|
|
 |
奈良井は今回で3度目。訪れるたびにほっとした気持ちになります。 |
|