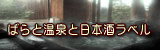自称「温泉同好会」3人で訪れました。塩原元湯温泉は今回が2度目(前回は隣の大出館に泊まりました)です。
部屋で浴衣に着替えてさっそく温泉へ。 |
| 岩風呂〜邯鄲(かんたん)の湯〜 |
| 【源泉名】 |
邯鄲の湯 (自然湧出) |
| 【泉質】 |
含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 |
| 【泉温】 |
48.1℃ |
| 【pH】 |
6.6 |
| 【湧出量】 |
2.5リットル/分 |
| 【効能】 |
切り傷、胃腸病、にきび、慢性便秘など |
|
 |
 |
元泉館といったらやはりこの岩風呂でしょう。
入口と脱衣所は男女別ですが、浴槽はひとつで終日混浴(宿泊客専用)です。
もちろん源泉かけ流し。こういう趣のある浴場に出会うと心がときめきます。 |
 |
 |
岩間から48℃の温泉が自然湧出しています。硫化水素臭が漂い、色は「濃緑乳灰色」とでも表現したらいいでしょうか。
湯舟の左隅にもうひとつ注入口があり、こちらは別の源泉(おろらくは「高尾の湯」。確認はしていません)のようです。 |
ここが湧出口の湯溜まり。仲居さんの話では飲用可で、朝食にはこの湯溜まりから汲んで炊いた「温泉お粥」が出るとか。
飲んでみると、胃薬をお湯で溶いたというか、「苦+塩+硫黄」の強烈な味。昔から「胃腸の名湯」といわれているそうですが、いかにも効きそう。明朝の温泉お粥も楽しみです。 |
 |
 |
 |
| 浴室はかまぼこ型をした面白い造りで、天井には湯気出しもあります。 |
|
| 岩風呂の入口近くにある飲泉所 |
 |
こちらはかなり飲みやすい。
これは後日『旅行読売』(2006年8月号)の野口冬人さんの記事で知ったのですが、「高尾の湯」を約10倍に薄めて供しているのだそうです。 |
|
| 檜風呂〜宝の湯〜 |
 |
| 【源泉名】 |
元泉館新掘 (掘削自噴) |
| 【泉質】 |
含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 |
| 【泉温】 |
57.4℃ |
| 【pH】 |
6.8 |
| 【湧出量】 |
20リットル/分 |
| 【効能】 |
糖尿病、婦人病、慢性気管支炎など |
|
 |
 |
男女別に浴室があります(宿泊客専用)。
邯鄲の湯とは対照的な乳白色の湯。注がれる時点では無色透明ですが、空気に触れて次第に白濁するようです。塩原でも珍しい間欠泉だそうです。 |
|
| 大浴場・渓流露天風呂〜高尾の湯〜 |
 |
| 【源泉名】 |
高尾の湯 (自然湧出) |
| 【泉質】 |
含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 |
| 【泉温】 |
50.6℃ |
| 【pH】 |
6.6 |
| 【湧出量】 |
72リットル/分 |
| 【効能】 |
リウマチ、神経痛、運動障害など |
|
| ここは別棟になっていて、日帰り入浴も受付けています。他の2つの浴場は24時間入浴できますが、ここの利用時間は6:30〜22:00となっています。 |
 |
 |
|
2面がガラス張りで、
広々としたすがすがしい浴室です。 |
 |
| 「高尾の湯」は乳緑色の湯。「邯鄲の湯」も「宝の湯」もすべて含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉ですが、微妙な含有成分の違いでずいぶん色が違うものです。 |
|
|
 |
 |
| 木々の緑が溶け込んだような露天風呂・・・いい雰囲気です。お湯の感触としては3つのうちで「高尾の湯」が一番ツルスベ感があるようです。 |
 |
 |
普段の仕事から解放され、
乳緑色の湯でくつろぐ
温泉同好会のT氏とN氏。 |
|
|
| 食事はこんな感じです |
 |
【夕食】 |
 |
|
| 【朝食】 |
 |
 |
| これが「温泉お粥」。とくに臭みもなく、昨晩飲みすぎた胃に優しく納まりました。 |
|
| この宿は「高尾の湯」目当ての日帰り入浴客も多いようですが、やはり名物岩風呂「邯鄲の湯」もいいし、「温泉お粥」も是非味わいたいもの。また訪れてみたい宿です。 |
| 【また行ってみたい度】 →こちらをお読みください |
| やなぎ夫: |
★★★★☆ |
やなぎ妻: |
未宿泊 |
|
2006年7月2日 |
|