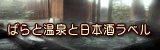| 織物参考館「紫(ゆかり)」 〜群馬県桐生市〜 (2006年4月2日) |
|
|
「西の西陣、東の桐生」といわれた織物の街
桐生の織物参考館「紫」を訪れました。 |
 |
 |
以前使用されていたノコギリ屋根工場に、多
数の織物の資料が展示されています。
このノコギリ屋根は一度に建てられたもので
はなく、工場が繁盛するにつれて増築されて
いったそうです。
かつては屋根の多さを競い合い、街の至る
所にあったノコギリ屋根工場も現在はほとん
ど見られなくなってしまいました。 |
|
|
ノコギリ屋根を内部から見ると
こうなっています→ |
 |
明り取りの窓はすべて北側にあります。南か
らの太陽光線は強すぎて、大切な織物を傷
めてしまうからです。
それと、今一度上の画像を見てください。
側面の窓はすべて曇りガラスになっていて、
しかも鉄格子がはめられています。これは
独自に考案した織物の柄を盗み見されない
ためだそうです。桐生織全盛時代、工場間
の競争がいかに激しく、また活気があったか
を窺い知ることができます。 |
|
| 館内は係りの方が丁寧に案内して実演や解説をしてくれます。 |
蚕(カイコ)の一生
蚕は英語で"silkworm"というんですね。
へんなところに感心してしまいました。 |
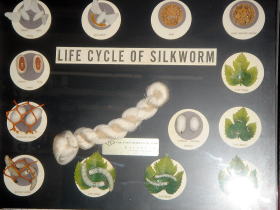 |
 |
鍋の中で煮た繭(まゆ)から
糸を巻き取る機械 |
|
 |
 |
| おもり機(はた) |
居座機(いざりばた) |
| 機織機の原型(BC560頃) |
5世紀頃中国から日本に伝わりました。手前の円弧状の
ところに座って織ります。 |
|
|
 |
高機(たかはた) |
居座機より高いのでその名が付いています。
一緒に説明を聞いて回った小学生が挑戦。 |
|
|
 |
八丁撚糸機(はっちょうねんしき) |
手廻しだったものを天明3年に岩瀬吉兵衛が水車動力
に改良し、その孫吉郎が揚枠の回転計を完成させたそ
うです。
|
|
|
| ジャンボ高機 |
 |
明治15〜20年にかけて使われた巨大な高機で、三人が
かりで織ります。体験させてもらいました。 |
 |
|
|
 |
 |
| 空引織 (平安時代) |
ジャカード機 (明治時代) |
|
フランス人ジャカールが発明。紋紙(穴のあいた紙)を使
って模様を織り込みます。オルゴールがヒントだとか。 |
|
|
 |
 |
| ピアノマシン |
| ジャカード紋織物に使う紋紙に穴を開ける機械です。 |
|
|
| 半高機とび杼(ひ)装置付 |
 |
イギリス人ジョン・ケイが発明(1733年)。杼とは横糸を
通す為の道具で、紐を引っ張ることによって杼を左右交
互に動かすことができる装置で、以前の3倍の速さで織
れるようになったことで大量生産が可能になり、産業革
命が起こりました。 |
| 果敢に挑戦・・・織機がほしくなってしまいました。 |
|
 |
 |
 |
| 藍染工房 |
発酵のための温度管理が重要だとか。「元気」を与える
ために日本酒を加えることもあるそうです。 |
|
 |
 |
| こちらは現在も稼動している工場 |
| コンピュータ管理で、海外向けの織物カレンダーを生産しています。 |
 |
以前は小学生が胸や帽子につける校章も
生産していたそうです。
懐かしかった・・・。 |
|
|